食品の開発において、私たちがどれほど品質に自信を持った製品を作り上げたとしても、それだけでは求める品質でお客様に製品を届けられない場合があります。その典型例が、異物混入です。たった一つの「異物混入」が全てを台無しにします。
食品は安全であり、安心して楽しめるのが何よりの前提です。しかし、一度でも異物混入が発生すれば、消費者の信頼は瞬く間に失われますその異物が、危険異物か非危険異物に関係ありません。その影響は、その製品だけでなく、企業のブランド価値全体を揺るがす深刻な問題となります。実際、異物混入を原因とする製品回収やメディア報道によって、長年培ってきた信頼が一夜にして崩れる事例も珍しくありません。穢れを嫌う文化的背景を持つ日本人に特有の現象かもしれません。
だからこそ、私たち食品業界のすべての関係者が認識すべきなのは、「異物混入をゼロにする」という揺るぎない決意です。それは単なる品質管理の一部ではなく、消費者との信頼関係を守るための使命そのものなのです。
食品工場における異物混入は、食品の安全性を脅かす深刻な問題とされます。なぜ、現代においても根絶できないのでしょうか?
答えは単純ですが、解決は容易ではありません。方法論を知らないからです。
異物は、食品中にあるべきでないもの あるはずがないものが混入することと定義されています。
戦後直後の1947年に制定された食品衛生法第6条(不衛生な食品又は添加物の販売等の禁止)の中に「四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの」として異物を初めて明記しました。
2014年の『食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針の改正』中では異物は人に悪影響を及ぼしうるガラス及び金属片等と具体的な有形物を挙げ定義しています。
一般的に異物とは目で見てそれと分かるもの、物理的な操作(溶解分離や比重差での分離等)で取り除けるものをいい、『食品衛生検査指針』第9章の中で「異物は、生産、貯蔵流通の過程で不都合な環境や取り扱い方に伴って、食品中に侵入または混入したあらゆる有形外来物という」をいい。異物を以下の3つに大別しています。
- 動物性異物 :虫、虫片、体毛、羽毛、哺乳動物や鳥類の排泄物、卵など
- 植物性異物 :植物片、木片、紙片、カビなど
- 鉱物性異物 :鉱物・岩石片、貝殻片、ガラス片、金属片、合成ゴム、合成繊維など
どれについても精神面を含め人に直接危害を及ぼす可能性があり、ガラス、金属等の異物は特に危険です。
そこで、リスク面からは異物を以下の3つに大別されます。
- 非危険異物 :異物自体は不快であり衛生的ではないが、健康への影響が少ないと判断されるもの。
- 危険異物 :喫食することにより生命や健康への影響が大きいと判断されるもの。
- 原材料由来物 :原料に由来する物質であるが、喫食した場合、健康への影響があると思われるもの。
以上のようなことは大抵の食品異物の書籍には書かれています。
さて、これで十分に全容はつかめるでしょうか?
私たちが日々の仕事や生活の中で、つい「知っているつもり」になってしまうことがあります。それは、一見すると自信を持っているように思えるかもしれませんが、実は非常に危うい状態かもしれません。
どうしてか?
それは、「知っている」と思っていることの中に、本当の理解が欠けている場合が多いからです。例えば、ある作業を何度も繰り返していると、その手順を暗記してしまいがちです。しかし、本当にその作業の本質的な理由や意味を理解しているでしょうか?
表面的にはうまくこなしているように見えるかもしれませんが、実はその作業の背景や目的をしっかり把握していなければ、いざ問題が発生した時に対処できなくなります。最初は小さなミスで済んだとしても、それが積み重なり、大きな問題に繋がることもあります。
「知っているつもり」という状態は、実は無意識のうちに成長を止めてしまいます。真に理解していることと、ただ知っているつもりでいることの違いは、成長に繋がらないことがあります。自分が本当に理解しているかどうかを常に疑い、深く掘り下げることが大切です。
そうしないと、いずれその「つもり」が通用しない瞬間が来てしまうのです。それが異物混入です。
私たちは、つい「これくらい知っている」と思ってしまうことがありますが、それが間違いを招く元になり得ることを忘れてはいけません。基本を見直し、実質的にどこまで理解しているのかを常に問い続けること。それこそが、長期的に成功するための鍵であり、自分の成長を支える土台となるのです。ですから、今一度、あなたが「知っているつもり」のことについて、少し立ち止まって考えてみてください。その理解が本当に深いのか、それとも表面的なもので終わっていないか。気づいた時には、もう一歩成長するチャンスが待っているかもしれません。
異物の全体と詳細の把握、異物自体とその混入経路の適正理解が異物根絶の第一歩です。
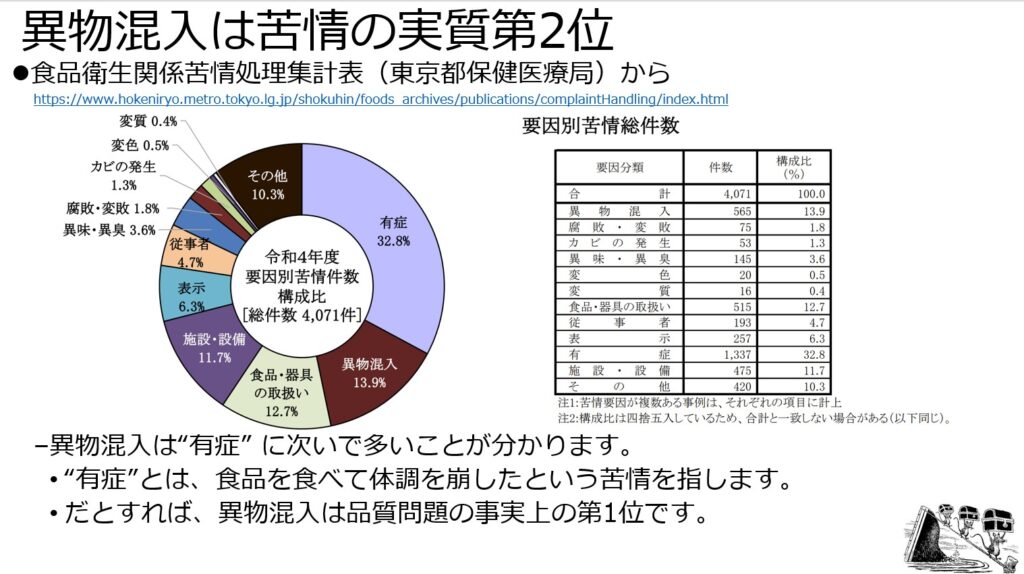
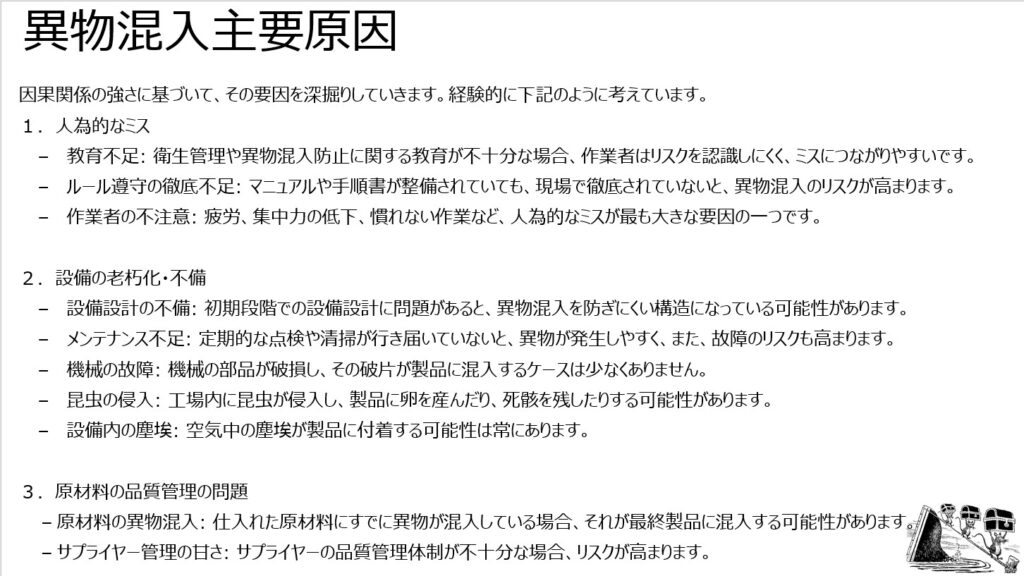
マス君お勧めの1冊:まずこれを読む!
食品製造・流通における異物混入防止対策: 危機予防から危機対応まで
私はこれで基本知識を習得しました。

