異物混入対策の策定基本手順は下記の通り。今更ながらかもしれませんが、基本を抑えましょう。
1.初期対応
- 対象商品の隔離
- 異物が混入した可能性のある製品を速やかに隔離し、出荷や使用を停止します。
- 異物の確認・分析
- 混入した異物を回収して種類や形状、材質を確認します(例:金属、プラスチック、ガラスなど)。必要に応じて、金属探知機やX線検査装置を使用して混入元を推測します。
- 出所の特定
- 異物が外部由来(原料や包装材など)か、内部由来(製造設備や作業環境)かを区別します。
- 記録の作成
- 発生日時、場所、異物の詳細、当時の状況を詳細に記録します
。
2.発生原因の追求
- 異物混入の根本原因を明確にするために、体系的な分析を行います。
- 特性要因図を用いて原因を掘り下げ、問題の本質を探ります。
- 「人」「機械」「材料」「方法」「環境」といった要因に分けて整理することで、抜け漏れを防ぎます
3.再発防止策の策定
- 原因が判明した後は、適切な対策を立てます。
- 設備や工程の改善
- 摩耗しやすい部品の交換スケジュールを短縮。
- 混入リスクが高い場所に異物除去装置を追加。
- 作業者教育
- 作業員に異物混入防止に関する研修を実施。
- 衛生管理基準(GMP)を再確認。
- 原料受け入れ時の検査強化
- 原料段階での異物検出を強化する。
4.改善策の実行と報告
- 改善の実施とモニタリング
- 策定した対策を計画的に導入し、全工程で実行します。その後、一定期間モニタリングを実施して改善策の効果を確認します(例:製品検査結果のデータ分析や異物検出頻度の変化)。
- 報告書の作成と共有
- 調査結果や対策内容を明確に記載した報告書を作成し、社内で共有します。必要に応じて、顧客や行政機関への説明資料としても活用します。
5.継続的改善
- 内部監査の実施
- 定期的に異物混入リスクを再評価し、予防策を見直します。
- 新たなリスクへの対応
- 原料や工程の変更時に新たな混入リスクが発生していないか確認します。
これ以上もこれ以下もありません。正しく理解してやるか、やらないか。理論と実践の追求です。
何がどこからどうやって来たのかを多角的に根本原因分析を行い、適切な対策をとる。それだけのことです。
答えは単純ですが、解決は容易ではありません。ここからは、方法論を説明します。
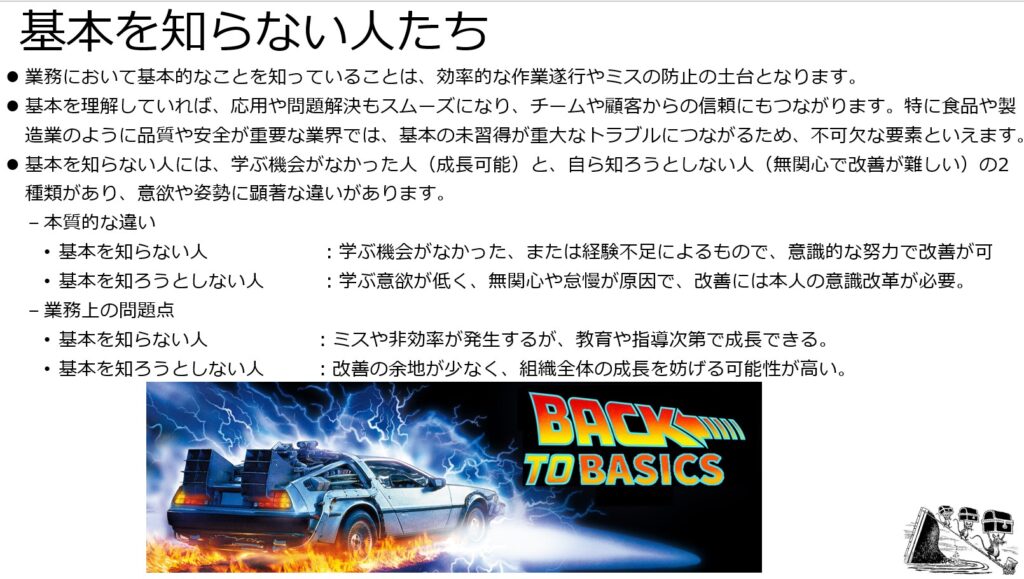
マス君お勧めの1冊:まずこれを読む!
食品製造・流通における異物混入防止対策: 危機予防から危機対応まで
専門性が高すぎて売れてないような気がしますが良書です。異物に関して勉強し直すならこれ。

