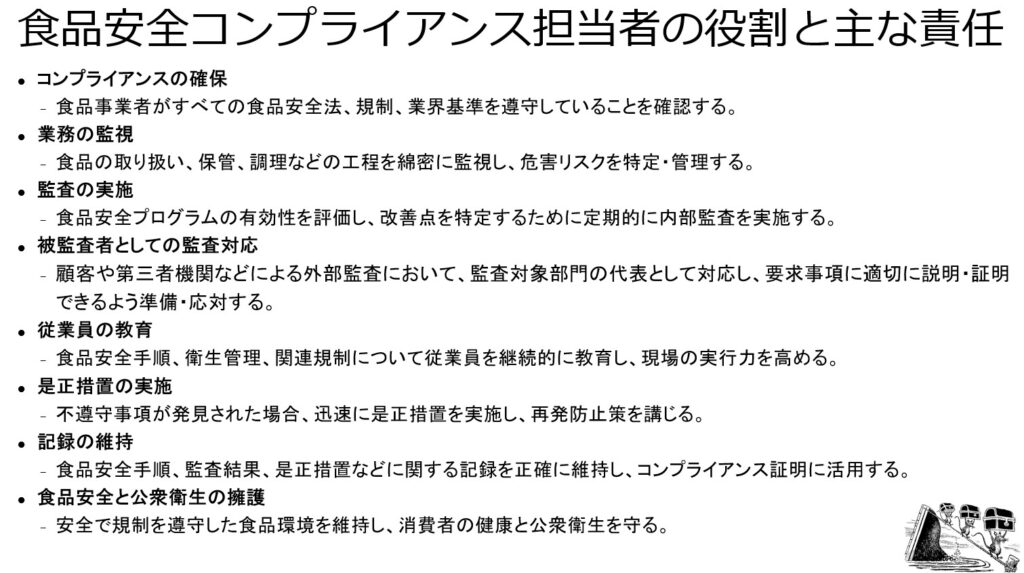ヨーロッパで監査者に同席した経験です。被監査者側には、2-3名の監査対応者が交代勤務の各シフト毎に選任されていました。無予告監査で訪問し、監査者側のバイスプレジデントと被監査者側のCEOの署名入り監査許可証を提示するとおよそ10分で被監査者側CEOの署名照合が財務部署に取られ会議室に招かれます。そうすると件の監査対応者が下記3点を告げます。
- 自分だけが正式な発言権を有すること。
- 安全に関する指示には従うこと。
- シフト間で監査対応者が交代するので引継ぎの時間が必要なこと。
監査はつつがなく進み、ほとんどの場合とても円滑でした。指摘事項に関しては、その理由の明瞭性が求められますが、監査者が説明を尽くせばそれで終わり。いかに対応するかは被監査者側の課題として対応責任が生じます。極めて公平で整然としています。とてもシステマティックです。
日本においても食品業界における安全・品質への要求は年々厳しさを増しています。取引先による食品安全システム監査も、その内容・基準ともに高度化しており、単なる形式的な確認だけでは対応が難しい時代になりました。このような環境の中で、当工場が顧客からの信頼を維持し、さらなる事業成長を目指すためには、「監査対応専門職」を設置することが急務と感じています。
現在、多くの食品企業での監査対応は品質保証部門が日常業務と兼任して行っています。しかし、日々の業務に追われる中では、監査準備や現場対応が後手に回り、属人的な運営になりがちです。結果として、指摘リスクの増加、対応品質のばらつき、さらには工場全体での食品安全レベルの低下を招く可能性が出てきています。
特に、近年の監査では、ルールが存在するだけでなく、それが「現場で正しく理解・運用されているか」「継続的な改善がなされているか」という実態を厳しく問われる傾向が強まっています。これらに適切に対応するためには、監査の専門知識と高度な現場調整力を兼ね備えた専任担当が不可欠です。
ここで言う専門知識とは、たとえば以下のようなものを指します。
- GMP(適正製造規範)やHACCP(危害分析重要管理点)、FSSC 22000など、各種食品安全規格の要求事項に関する正確な理解
- 監査基準に基づき、書類(手順書、記録)と実際の現場運用との整合性を的確に評価する力
- 逸脱(ルール違反)発生時のリスクアセスメントと、是正・予防措置策定に関する実務知識
- 監査中の質疑応答において、背景や意図を押さえた上で簡潔・的確に説明できるコミュニケーション力
監査対応専門職を設置することにより、工場にはいくつかの重要な変化が期待できます。
まず、監査要求事項に沿った事前準備を確実に行い、指摘リスクを大幅に低減できるようになります。監査中も、質問に対して的確かつ自信を持った説明ができることで、取引先からの評価が向上します。さらに、監査後の指摘事項への迅速な是正対応が可能となり、工場の品質・食品安全レベルの持続的な向上にもつながります。
また、監査対応専門職の設置は、原材料サプライヤーに対する監査の質向上にも直結します。
サプライヤー監査においても、単に提出書類を確認するだけではなく、現場実態との整合性や、リスク管理体制の成熟度までを見極める力が求められています。
監査対応専門職は、日頃から自工場に対する厳しい監査に対応し、要求水準やリスク感度を高めているため、同様の視点でサプライヤーの監査を行い、より実効性のある評価と指導ができるようになります。これにより、供給される原材料の品質・安全性リスクを事前に察知・管理できるため、重大なトラブルの未然防止につながります。さらに、サプライヤーに対する改善要求も具体的かつ建設的な内容となり、サプライチェーン全体のレベル向上を促進することが可能となります。
加えて、監査対応専門職は単なる「監査要員」ではありません。その役割は、監査対応にとどまらず、工場全体の食品安全マネジメントシステムを実効的に機能させるための「推進役」でもあります。具体的には、監査を通じて得た課題や改善要求を整理・分析し、それを基に社内の運用改善をリードしていきます。
さらに、各部門に対して教育・訓練を行い、現場従業員一人ひとりが食品安全を自らの課題として認識し、行動できるよう促す役割も担います。つまり、監査に「受け身」で対応するのではなく、監査を「工場・サプライチェーン改善のきっかけ」として能動的に活用するための中心的存在となるのです。
監査対応専門職が育成され、工場内に根付くことで、単に「監査を乗り切る」だけではなく、持続的な食品安全文化(Food Safety Culture)を築くことが可能になります。これは今後、企業価値の向上、取引先からの選ばれる理由づくりに直結する大きな競争力となるでしょう。
仮に監査で重大な指摘を受けた場合、最悪の場合は取引停止に至るリスクも否定できません。それは単なる工場単位の問題ではなく、企業全体の信用問題へと波及します。逆に、日ごろから監査に強い体制を築き、顧客からの信頼を確実に勝ち取ることができれば、新たな取引機会の拡大や、他工場との差別化といった経営的メリットも生まれます。
ぜひ「監査対応専門職」の設置をご検討してみてください。